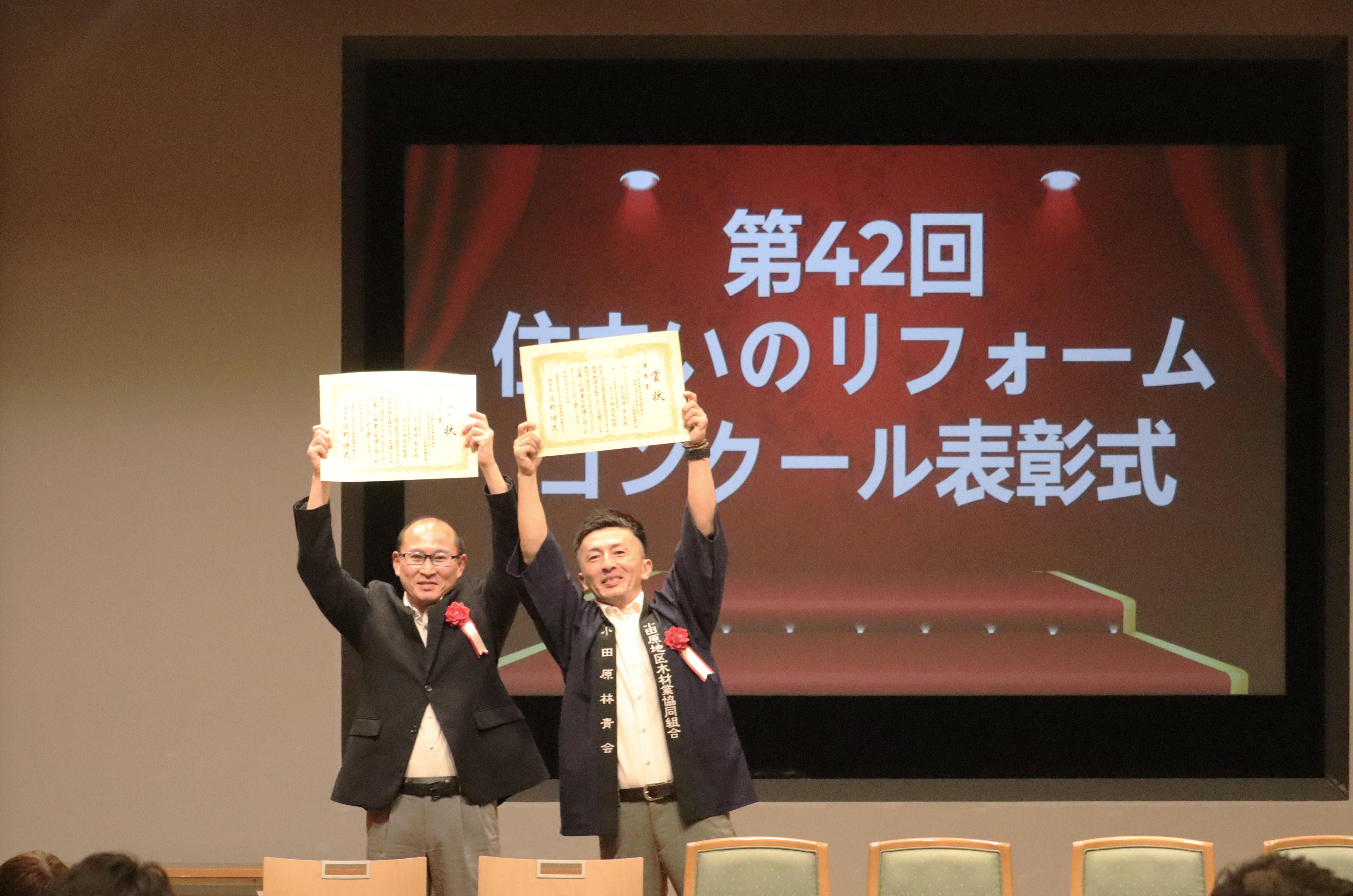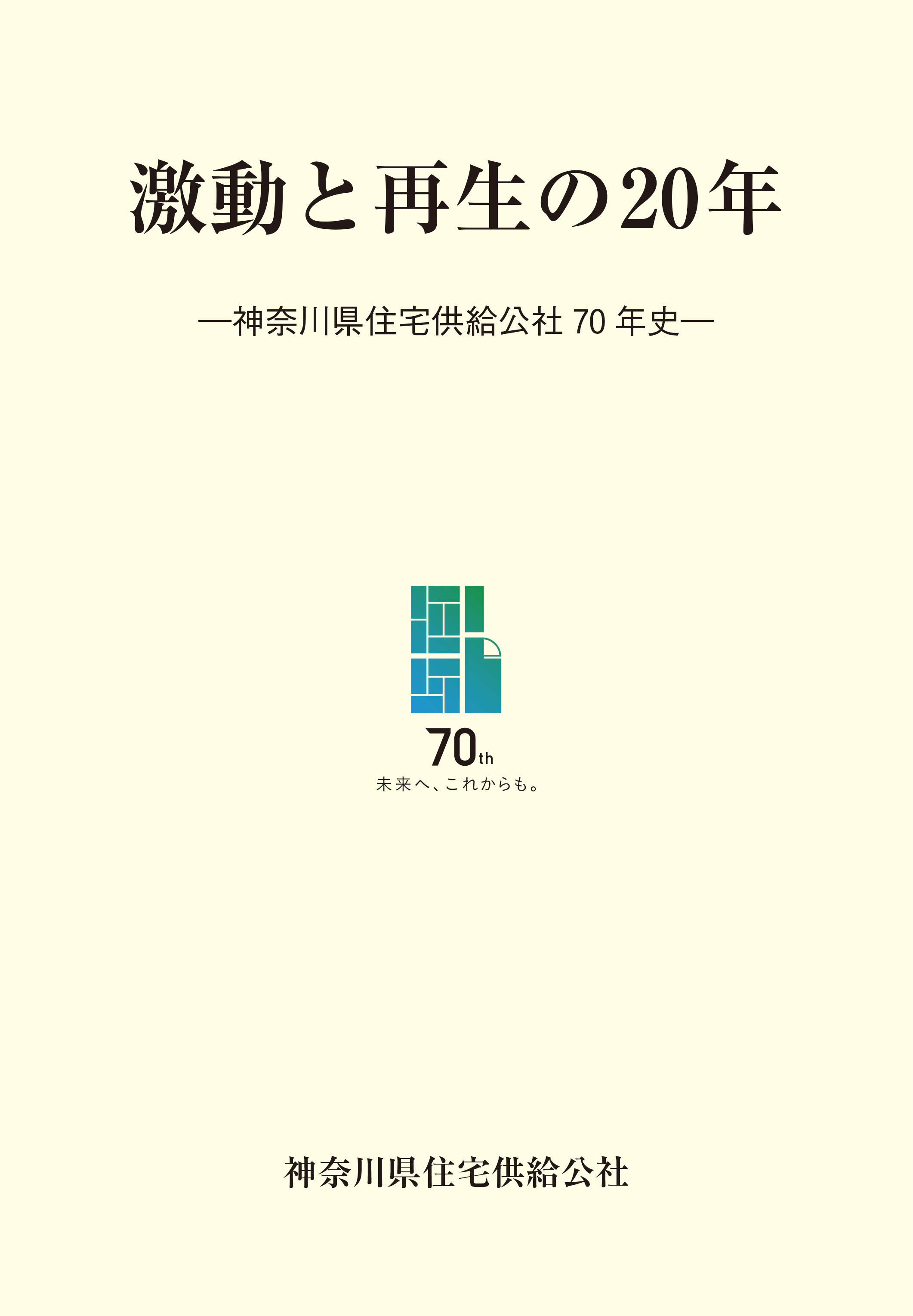ハラスメント防止研修で学ぶ「働きやすい職場づくり」
公社のこと2025.09.29
神奈川県住宅供給公社では、年に2回、公社で働く全ての人を対象にコンプライアンス関連の研修を行っています。
今回は、7月実施したハラスメント防止研修についてご紹介します。
ハラスメント防止研修は、全員が同時に受講することは難しいため、研修は3回に分けて実施。各自が自身の業務の都合に合わせて参加できるようにしています。
研修は講義だけでなく、グループワークやディスカッション、実践演習を交えて進めます。
そのため、対面とオンラインでは理解度や体験に差が生まれてしまい、本来の目的が十分に果たせないことを防ぐため、基本的には対面参加を原則としています。
ただし、やむを得ず参加できない場合は、研修を撮影した動画を視聴することで受講できる仕組みも用意しています。
研修は、総務広報課長から「セクハラやパワハラといった限定的なハラスメントだけではなく、幅広く意識をアップデートしてほしい」との挨拶からスタートしました。
ケーススタディで考える日常の気づき
今回の研修は、具体的な事例をもとにディスカッションするケーススタディが中心。
グループワークでは講師からの「自分と違う意見も否定せず、遮らずに聞く」というアドバイスを意識して進めます。
グループワークでは、「良好な職場環境とは、話しやすい雰囲気があることじゃないかな」「コミュニケーションを大切にするという面で、雑談も大事だと思う」といった意見が出て、日常の何気ないやり取りも、職場づくりにつながることに気づかされました。
パワハラの背景を考える
パワハラに関するビデオを見て、グループでの交換も行いました。
ポイントは「双方の視点から考えること」。
「自分は正しい」もしくは「自分が間違っている」など、無意識の思い込みがハラスメントにつながることもあります。
同じ場面を見ても、人によって受け取り方が違うのが興味深く、ディスカッションのたびに新しい気づきがありました。
ロールプレイで体感する難しさ
実際の職場で起こりうる状況でのロールプレイも実施。
意図せず誤解を与えてしまうことや、自分の考えだけで判断してしまう危うさを体感できました。
「若手だから・べテランだから」「女性だから・男性だから」「正規雇用だから・非正規雇用だから」などのアンコンシャスバイアスは排除して、互いの立場や背景を理解することの大切さを改めて実感しました。
研修の締めくくりは行動宣言
最後には「職場のハラスメント防止のために、自分はこう行動する」という行動宣言カードを記入。
今回の研修を通して、ハラスメント防止はルールを守るだけでなく、日常の関わり方や互いの理解、周囲の気づきやサポートも大切だということを実感。
小さな気づきや声かけ、日々のコミュニケーションが、誰もが安心して働ける職場につながることを改めて確認しました。
公社では、これからも公社で働くすべての人が安心して働ける職場環境づくりに取り組んでいきます。